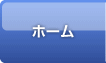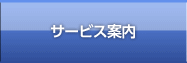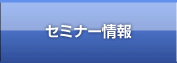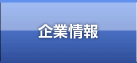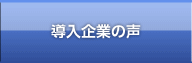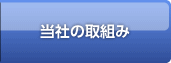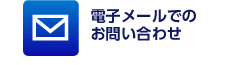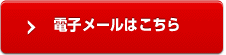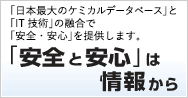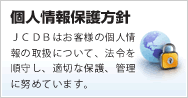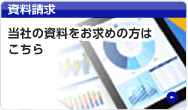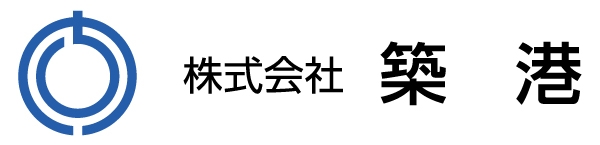四国化成工業株式会社

「化学品」と「建材」を主な事業領域とする四国化成グループの中で、「化学品」事業を受け持つ四国化成工業。主な事業内容は無機化成品/有機化成品/ファインケミカルとなっており、タイヤの原料やプール水の殺菌消毒剤、スマートフォンやパソコンなど電子部品の材料をはじめ、身近な商品の中間原料として暮らしを支える企業です。
情報収集の非効率性から来る「見落としの不安」が大きな課題だった。
 Chemlinked Japanの導入以前、四国化成工業では化学物質法規制情報の入手を複数の情報ソースに依存していた。それぞれの情報入手先にあたって収集した情報を取捨選択する形で取りまとめていたため、情報収集に時間がかかると同時に情報のモレとダブリを完全に排除することができなかったという。ダブリはともかくとしてモレ、すなわち見落としが発生した場合は危機的な状況に陥る可能性もゼロではなかった。
Chemlinked Japanの導入以前、四国化成工業では化学物質法規制情報の入手を複数の情報ソースに依存していた。それぞれの情報入手先にあたって収集した情報を取捨選択する形で取りまとめていたため、情報収集に時間がかかると同時に情報のモレとダブリを完全に排除することができなかったという。ダブリはともかくとしてモレ、すなわち見落としが発生した場合は危機的な状況に陥る可能性もゼロではなかった。
また、その当時は化学物質法規制情報の収集担当者の経験とスキルに依存する部分が大きく、情報の信頼性などは「彼が選んだ情報なら大丈夫だろう」という暗黙の了解で担保されていた。しかしいかに精通した担当者であれ、異動の日はいずれやって来る。業務の引き継ぎを丁寧に行ったとしても、彼の経験とスキルを引き継げるわけではない。
それら一連の課題をどう解決すれば良いのか、と動き始めた新しい担当者の目に留まったのがChemlinked Japanだった。
かつては常に不安と隣り合わせの属人的な業務だった。
Chemlinked Japan導入のきっかけは2023年8月、私が化学物質法規制情報の収集担当として異動してきたことに端を発します。それまでの弊社における化学物質法規制情報収集に基準やルールというものは特になく、経験豊富な前任担当者がこれは重要であろうと思われる情報をメルマガやニュースレター、当局のWebサイト、業界情報誌、そしてコンサルタント主催のセミナーなどからピックアップしていくというものでした。
その流れを引き継いでからの私は、当該分野の知識や経験が少なかったこともあり、常に不安と隣り合わせでした。「これらの情報入手先だけで必要な情報を網羅できているのか」「直近の法規制改正を見落としていないか」「情報収集に時間がかかりすぎていないか」など、疑問は枚挙に暇がなく、情報収集方法の改善は喫緊の課題だったのです。
現部署への異動前、私は工場で品質管理業務の標準化を推進して行く立場だったこともあり、その経験を活かして法規制情報をより効率的に収集・管理する方法の検討を開始しました。
そして上司へ問題提起を行うと共に関係者へ説明を進めつつ、速報性・網羅性・信頼性を兼ね備えた情報源のリサーチを行う中で出会ったのがChemlinked Japanでした。
インドの新たな化学品規制情報を知ったのが発効の2週間前だったことも。
Chemlinked Japan導入に至る少し前のことです。お恥ずかしい話ですが、2023年10月にインドで成分開示が義務化された際、その情報をキャッチできたのがなんと規制発効日の2週間前だったということがありました。その時は心底焦りましたが、とにかくなんとかしなければと大急ぎで対応を協議してどうにか乗り切ったという苦い思い出があります。その時、今までの情報収集方法ではやはり限界があるのだということを改めて痛感しました。既に新たな情報源のリサーチには入っていたのですが、すんでのところで間に合わなかったということです。それだけに情報収集を効率化し、見落としを防ぐ仕組みの構築が急務であるとの思いを新たにしました。
Chemlinked Japan導入の決め手は総合点の高さ
 他社さんの提供されている情報提供サービスも比較検討しましたが、Chemlinked Japanを採用するに至った理由は総合点の高さですね。2023年11月、まずはスタンダード(1名)で契約して導入を開始しました。
他社さんの提供されている情報提供サービスも比較検討しましたが、Chemlinked Japanを採用するに至った理由は総合点の高さですね。2023年11月、まずはスタンダード(1名)で契約して導入を開始しました。
まずは各国の法規制ニュースがまとめて提供される点。最新の規制改正情報を迅速に確認できるため、重要な改正情報を逃さずに把握できます。ニュースごとに内容をイメージできる画像がついているため直感的に理解しやすいことに加え、記事も詳細に書かれているので取りこぼしがありません。導入があと少し早ければ、インドでの規制情報に関わるドタバタも未然に防ぐことができたでしょう。
次いで、幅広い国・地域の法規制情報をカバーしていること。中国を始めとするアジア各国の化学関連情報提供サービスと銘打っていますが、実際にはEUや米国、ブラジル、チリなど世界各国の規制情報も確認できるので大変助かっています。
そして当局のURLリンクや法令原文の情報がしっかり記載されていることによる信頼性の高さ。一次情報である公式情報へのアクセスが容易なので、正確な情報を基に確実な対応を進めることができるようになりました。
特筆すべきは文章の読みやすさ。海外発信の情報がメインですから、翻訳の精度がたいへん重要です。Chemlinked Japanは専門知識がなくても理解しやすい言葉で表現されているため、どこの部門に所属している人でも活用しやすいという大きなアドバンテージがあります。
導入直後に高評価、わずか2ヶ月で関係部門全体での活用に。
2023年11月のChemlinked Japan導入時は、化学物質法規制の情報収集に使おうというのが当初の目的でした。導入の結果、情報見落としリスクの軽減や情報収集の時間の短縮、全社的な知識レベル並びに情報収集力の向上など、期待通りの成果に繋がり、何よりも「確実に情報をキャッチできる」という安心感が生まれました。
そして実際に使い始めてみると、Chemlinked Japanは他部署でも活用できるツールでもあるということに気づきました。
私が工場で品質管理の業務に就いていた頃、つまり情報を受け取る実務者側だった時には「情報の内容が専門的すぎて解りにくい」ということが少なからずありました。内容は良く理解できないものの、対応はしなければならない。それでも業務は回りますが、できれば実務者が主体的、能動的に情報を取りに行って対応できるような仕組みが理想です。また、いかに優れたツールでも、ただ各所へ配るだけではどれだけ活用してもらえるか分からないということもあります。そこで、Chemlinked Japanの導入をきっかけとして、運用ルールと情報活用の枠組み、さらに法規制の初心者でも気軽に利用できるフォロー体制をしっかりと組んでいこうという流れになりました。
そして導入からわずか2ヶ月後に20名のライセンス契約に切り替えて、法規制の専門部門だけでなく品質管理部門や研究開発部門、営業部門にもアカウントを配布。その結果、各部門から上がってきた評価はたいへん高く、利用者数をもっと増やせないかという声まで上がってきました。そして現在(2025年4月)の利用者は30名。
Chemlinked Japan活用の幅は今後ますます広がって行くであろうと確信しています。
Chemlinked Japanがもたらした社内の意識変化とスムーズな課題対応力
Chemlinked Japanの導入前、法規制情報は担当部門である研究企画室が配信する形でしたが、現在は各部門がそれぞれChemlinked Japanにアクセスし、必要な規制情報や該当する物質を自らチェックしに行くようになりました。これはひとえに見やすいWebサイト設計と理解しやすい記載内容のおかげです。
また法規制は重要な情報ですが、特に初心者にとっては難解でとっつきにくいものです。そこで、Chemlinked Japanの最新ニュースを取り上げ、疑問点の解消や対応方針の策定、実務者間の意見交換を定期的に行う部門横断ミーティングを研究企画室主導で毎月1回開催することにしました。このミーティングの初めには毎回「自由に話しましょう」と声をかけ、まず話しやすい雰囲気を作ることで気軽に意見できる場の醸成を心がけています。
その甲斐あって、疑問点の解消や対応方針の策定を定期的に行うことで法規制に対する理解が深まり、各人が迅速な意思決定を導けるようになってきました。時間的な制約と負担はあるものの、自由に意見交換・質問できる場としてのメリットも大きいと実感しています。
使い勝手の良いツールの導入と、運用をサポートする社内体制。この両輪が連携して稼働するようになった結果、以下に挙げる3つの大きな効果が現れました。
①規制対応へのスピードアップ→課題対応がスムーズに進むようになった
②法規制に対する意識のハードルの低減→社内での理解度が向上した
③コミュニケーションの活発化→定期ミーティングを通じて関係部署間の協力体制が強化された
そして各部門からは「今後もミーティングを継続して欲しい」「法規制に対してこれまで以上に迅速に対応できるようになって助かっている」「他の人のニュースの捉え方を知ることができて勉強になる」などの好意的な意見が寄せられています。Chemlinked Japanの導入をきっかけに、社内の法規制対応の姿勢そのものが変わったと申し上げても過言ではないでしょう。
それともう一点、Chemlinked JapanにはWebサイト内に用意されているフォームを使ってコンサルタントに質問できる機能が用意されていて、これがたいへん役立っています。基本的に「掲載記事内容の範囲内での質問に限る」という制限はありますが、記事内容についての解釈はこれで正しいかどうかの確認や、記事から派生した疑問についてもある程度対応していただけるのは大きなメリットですね。
試行錯誤を繰り返しながら最適解を見つけたい
 Chemlinked Japanの導入と社内体制の構築により、社内の情報収集・共有体制を確立し、化学物質法規制の変化にも迅速かつ網羅的に対応できる環境がようやく整いました。
Chemlinked Japanの導入と社内体制の構築により、社内の情報収集・共有体制を確立し、化学物質法規制の変化にも迅速かつ網羅的に対応できる環境がようやく整いました。
また情報収集のルールがしっかりと確立したことで、今後、法規制情報の担当者が変わることになった際でも、以前のような不安や心配なしに業務をスムーズに引き継げるようにもなったと思います。
弊社ではそれらを足掛かりとして、試行錯誤を繰り返しながら、引き続きChemlinked Japanのさらなる活用方法を模索していく予定です。現在着手し始めた社内データベースの改善や、今後は生成AIなども併用しながら情報管理の高度化も進めていく予定です。その実現には化学物質管理と情報技術の両方に精通したパートナーの協力が不可欠と認識していますので、JCDBさんのご助力に大きな期待を寄せております。