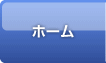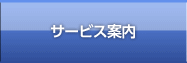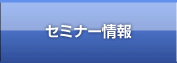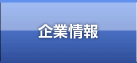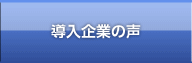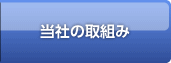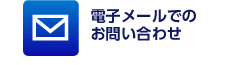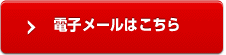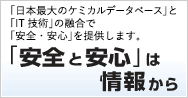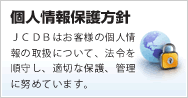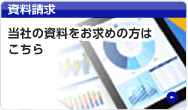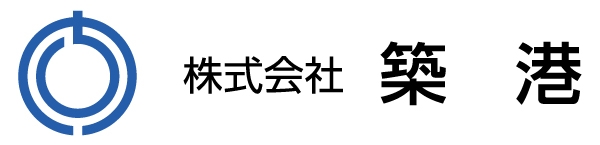株式会社カービューティープロ 様
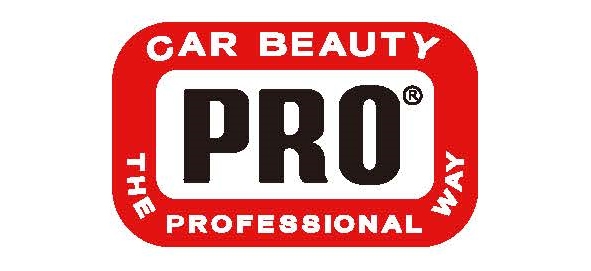
英文のSDSをベースに自社で日本の法規制に合致した日本語SDSを作成するために導入
以前の和文SDSはすべて自社で作成されておいでだったとか?
輸入時に添付されてくる英文SDSを直訳して作っていました。
導入いただいているサービス
クラウド型SDS作成支援サービス「ezSDS」
JCDBのSDS作成ノウハウとFQSS(富士通九州システムサービス)が得意とするクラウド環境を利用した、新しい形のSDS作成支援ツール。JISZ7253に基づいたSDS及びラベルの原案が簡単に作成できる。クラウド型+従量課金制でサーバ等を導入することなく、しかも低コストでの運用が可能である。 以前はアメリカから輸入した際の英語版SDSを日本語に直訳したものを添付していました。ところが、2005年の労安法(労働安全衛生法)改正を受けて翌年の2006年12月にGHSに対応したラベル表示とSDSの交付が義務付けられることで、そのままでは対応できなくなる可能性が高いことが次第にわかってきました。現在はだいぶ改善されたのですが、当時アメリカで発行されたSDSはCAS番号は記載されていても、それ以外は最低限の情報しか載っていないケースが多かったからです。
以前はアメリカから輸入した際の英語版SDSを日本語に直訳したものを添付していました。ところが、2005年の労安法(労働安全衛生法)改正を受けて翌年の2006年12月にGHSに対応したラベル表示とSDSの交付が義務付けられることで、そのままでは対応できなくなる可能性が高いことが次第にわかってきました。現在はだいぶ改善されたのですが、当時アメリカで発行されたSDSはCAS番号は記載されていても、それ以外は最低限の情報しか載っていないケースが多かったからです。
当社はコーティング剤を始めとするカーディテイリングケミカルカンパニー、アメリカBAF Industriesの日本総代理店なのですが、輸入した製品をそのまま販売するだけではありません。ドラムで輸入したものを小分けでボトリングした上で日本語のラベルを貼り、当社の製品として販売するケースもあります。そのため、日本の規制にしっかり合致した日本語版SDSが不可欠だという結論に至りました。
そんな折、ある取引先から「労安法が改正されるとSDSやラベルの記載内容がだいぶ細かくなるけれど、御社は大丈夫ですよね?」と脅しのようなアドバイスをいただいたことが契機になりました(笑)。そのうち各社から同じお話をいただくようになり、これは本腰を入れなければならないということがわかったのですが、ちょうどそのタイミングで工業会に加盟している方からJCDBさんをご紹介いただくことができました。
ezSDS導入までの経緯をお聞かせ願えますか

最初のスタートはezCRIC。SDS作成ツールがあることも初めて知りました。
それまでは何もかも手探りでおっかなびっくりでした。表示義務と言われても良くわからなかったし、SDSを作成するためのツールという選択肢があるということも知りませんでしたからね。英文のSDSをベースに、自社で日本の法規制に合致した日本語SDSを作りたいと相談したのが始まりでした。JCDBさんとのお付き合いが始まったことで、きちんと裏付けのあるSDSの作成が初めて可能になったのです。
最初に導入したのはez CRIC(化学品の該当法律を一発検索できるソフト)。ez CRICを使い始めたことでCAS番号から必要な情報を検索して確認出来るようになりました。ただし、確認の結果、法規に抵触する箇所が見つかったときは自社だけで対応することができず、懇意にしている同業他社へその都度アドバイスを求めに向かうことで対処していました。
当初はそれでも良かったのですが、次第に回数が重なるようになってくるとさすがにご迷惑がかかります。そこで、あらためてJCDBさんに「英文のSDSをベースに、日本の法規制に合致した日本語SDSを自社で作りたい」と相談したところ「こちらはいかがでしょう」とお薦めいただいたのがMSDSnaviでした。
MSDSnaviはラベル表示とSDSに必要な法規のデータや物質情報データベースを搭載したノートPCをレンタルして使う形式のサービスで、SDSを手軽に作成できるシステムとしてはその当時唯一のものでした。
関連法規チェックやGHS分類も自動的に行ってくれる機能を持ち、データ更新やサポートなどもオールインワンで提供されるため、当社が利用するにはまさにジャストフィットの製品です。そこで早速導入に踏み切ったのですが、導入の結果は予想以上の効果でした。ラベルやSDSデータを作成するヒントが出てくるため、それをベースに当社として伝えたいことを付加する、というプロセスを踏むだけでSDSが作成できるようになったのです。MSDSnaviの導入で作業性と精度が格段に上がりました。
ezSDS導入の効果についてお教えください。

スペース効率、タイムリーな情報、コストセーブの3つです。
MSDSnaviは大変使い勝手が良かったのですが、使っているうちに幾つか改善できたらいいという点が出てきました。
そのひとつはスペース効率。ノートPCというのは意外と場所を取るんですね。デスクの上には既に自分のPCがありましたから、そこへもうひとつPCが来るとなるとかなり圧迫感があります。さらに操作者が変わるたびにノートPCを持って移動しなければならないというのも手間でした。
次はアップデートの手間。MSDSnaviはメールで示されたアドレスへアクセスしてアップデータをダウンロードするという方法だったので、アップデートのし忘れや見落としが発生する可能性が払拭できませんでした。
そして最後はコスト。SDSとラベルは新製品を発売するときに欠かせませんが、当社はメーカー専業ではないため、年によっては新製品がひとつもないというケースもあります。利用頻度を考慮すると機能的にはもう少しライトでもいいのだが…と考え始めていたときに知ったのがJCDBさんのezSDS。検討した結果、まさにこれこそ求めていたサービスであることがわかりました。そこで2015年に切り替え導入した結果、気になっていた点が一挙に改善できました。ezSDSはクラウドサービスなので外出先からもアクセスできます。得意先での商談中にSDSを見たいというときにもすぐに参照できるようになったのも大きなメリットでした。
ちなみにSDSの参考文献等を記載する箇所へはJCDBさんの社名とezSDSを表記するようにしています。詳しくないお客様は「きちんと裏付けのあるものなんだ」と思ってくださいますし、専門的な知識をお持ちのお客様であれば「JCDBさんのデータを使っているなら間違いない」と、どちらの場合でも胸を張ってお出しできるわけです。ezSDSを使っていれば私たちも安心ですし、お客様の安心も担保できるという意味でとても役に立つサービスだと思います。営業のサポートツールとしても有用ですね。
なお、当社で行っているラッピング加工の原反メーカー(エイブリィ・デニソン)がアメリカにあり、そこはカーケア用のケミカル製品を数種類持っています。日本法人が輸入販売を検討したときにSDSの作成にかなり注意を払う必要があることをお伝えしたところ「ならばきちんと作れる御社で扱ってもらうことはできませんか」と独占に近い形での販売ができることになりました。日本法人にとっては安心、当社にとってはビジネスチャンスと、互いに良い関係が結べたのもezSDSのおかげです。
今後の展望やご要望についてお教えください。
SDSの精度を上げてゆくための取り組みを行っています。
ezSDSを活用して当社で作成したSDSやラベルは見直しを含めると100種類以上にのぼります。ちょうど会社の統合を行った時期と重なったこともあり、良い機会なので社名表記の変更と同時に既存製品のGHSも最新表記に差し替えようということになりました。
現在は法規改正の動向を含め、ezSDSの最新情報を定期的に確認するようにしています。ともすると後手に回りがちではありますが、SDSやラベルを更新すべきときは速やかに更新し、販売先、取引先に対してもできるかぎりタイムリーな情報発信をしていこうと心がけています。
また、一度作成したSDSやラベルの記載内容見直しも同時に行っています。基本データはezSDSから引き出して転記していますが、自分たちで入力しなければいけない情報もありますからね。法規制や記載内容規定についての理解が進むほど、過去に作成したものがほんとうに正しいかどうかを再度検証する必要があるということがわかってきました。現在は表記順や言い回しなどの統一を含め、フォーマット化を図っている最中です。