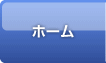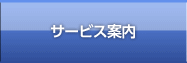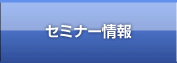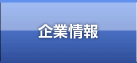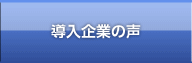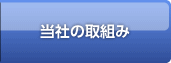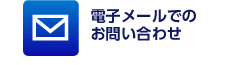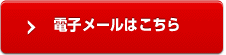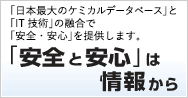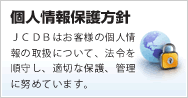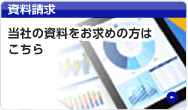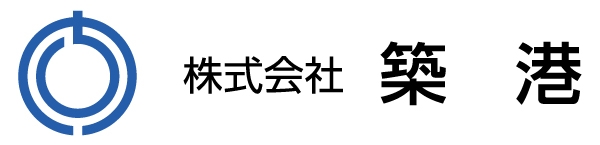株式会社クラレ 様

化学物質マネジメントシステムを検討し、導入を決めた社内システムと連携して活用できるデータベースとして導入。
株式会社クラレ 様概要
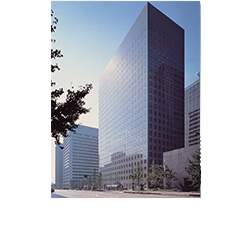
CSR本部
CSR部
品質保証グループ
グループリーダー
植村 純一 様
CSR本部
CSR部
品質保証グループ
立花 美樹 様
※所属・役職は取材時のものとなります。
LOLIを活用されるようになったきっかけを教えてください。
全社で取り扱う化学物質情報の一元管理を始めたことです。
導入いただいているサービス
LOLIデータベース
LOLIは、世界115カ国以上を対象にした5,100以上の海外法規制リストとEHS(*1)リストや海外インベントリーを搭載し、検索・参照・出力できるデータベースです。
*1:EHS Environmental, Health and Safety 環境・健康・安全 LOLIを活用するようになったのは2012年、自社で取り扱う化学物質情報を一元管理する社内システムの導入がきっかけです。数社の化学物質マネジメントシステムを検討し、導入を決めた社内システムと連携して活用できるデータベースがLOLIでした。それまでは社内カンパニーや各事業部が個別に化学物質情報を管理しており、私たちCSR部も独自のシステムを運用していました。以前はそれでも良かったのですが、製品が増え、ビジネス対象となる地域が増えてくるに従って、適用となるレギュレーションも増加してきていました。
LOLIを活用するようになったのは2012年、自社で取り扱う化学物質情報を一元管理する社内システムの導入がきっかけです。数社の化学物質マネジメントシステムを検討し、導入を決めた社内システムと連携して活用できるデータベースがLOLIでした。それまでは社内カンパニーや各事業部が個別に化学物質情報を管理しており、私たちCSR部も独自のシステムを運用していました。以前はそれでも良かったのですが、製品が増え、ビジネス対象となる地域が増えてくるに従って、適用となるレギュレーションも増加してきていました。
製品を作って販売するに際しては「どんな法令・法規や基準などに対応すればよいか」ということがきちんとわかっていれば、それを行えばよいわけです。ところが、特に新しい分野で新しい製品を作って販売しようとする場合には、該当する可能性のあるルールを全て自分たちで調べていかなければなりません。言い換えれば、あるルールを知らなかった、または見落としていた場合、結果的にそのルールに適合しない製品になってしまうという可能性をはらんでいるということです。そうした観点から、すべてのルールを捕捉して適切に対応するために情報を統合して管理する必要性が高まり、導入に至りました。
LOLIをどのように活用しておいでですか?
 デスクトップだけではなく、自社システムと連携した使い方もしています。
デスクトップだけではなく、自社システムと連携した使い方もしています。
現在、弊社におけるLOLIデータベースの運用方法は2パターンあります。ひとつはクラレ及び関連企業全体で利用するために、全社で扱う化学物質情報を管理する社内システムとLOLIをリンクさせる形で使うパターン。LOLI Desktopに格納されている海外法規制リストやEHSリストなどはEXCELやWORDといった電子ファイル形式で出力できますので、必要に応じてアウトプットして活用しています。
そしてもうひとつはLOLI Desktopからアクセスするパターン。LOLI Desktopからアクセスできる人数には制限があるため、全社から法令対応等の相談を受けるCSR部、そして特に活用度の高い部署や希望部署等にアクセス権を配布して運用しています。CSR部は社内全体を俯瞰して見る立場にありますので、その意味ではLOLIにアクセスしている時間が一番長いのは私たちかも知れませんね(笑)。
社内システムやLOLIの使い方についての説明会をきめ細かく行われているとお伺いしています。
使う人によって必要度が違うため、理解を促すための工夫を重ねました。
私たちCSR部にとっては、社員もまたステークホルダーの一員です。彼ら全員を顧客とみなして考えれば「新しく導入するデータベースは顧客満足度を高めるツールである」ということになりますので、それを周知させて理解を導き、活用方法を覚えてもらうのも私たちのミッションであると言っていいでしょう。
社内システムは全社で同時に導入したのですが、製品の種類やそれを販売するお客様は多岐に渡るため、部署や業務内容によってデータベースの必要度は大きく異なっています。化学物質そのものを商品として扱っている部署は、業務上、データベースの情報が必要になるということもあり、こちらからのアプローチを待つまでもなく積極的に利用してくれました。一方、日常業務の中でデータベース検索を行う必要がそれほど多くない部署の場合はそうもいきません。利用頻度が低いことから、いざ実際に必要な局面がやってきたときにスムーズな運用は望めないのではないか?という懸念がありました。
そこでJCDBさんにもご協力いただき、実際に起こりうる課題を例示し、その解決策としてデータベースがどれだけ有用かということを説明する─という手法を採り、できるだけ平易でわかりやすい社内説明会を行うことにしました。システムの全体像や概念などの説明から始めるのではなく、社内システムやデータベースを活用することで生まれるメリットを具体的にイメージしてもらえるようなアプローチですね。例えば、法令改正が行われる場合、どんなタイミングで何がどう変わるか、データベースを活用するとそれらの確認がどれだけラクになるか、というようなケーススタディです。その結果、データベースの活用度が向上してきていると思います。
必要度や専門知識のレベルが異なる人たちを一同に会して行うため、どのレベルに向けて説明するか、基準を置くかは今でも試行錯誤の繰り返しです。全員が同じように理解する勉強会を開催するのは事実上不可能ですので、都度、参加者の顔ぶれを見たうえで説明内容を臨機応変に変えるようにしています。
導入いただいた感想をお伺いできますか。
実利のみならず、意識改革の点でも大きな効果がありました。
導入の効果としては、危険有害性情報や各国のインベントリー情報などを一覧形式で閲覧できるようになったことがまず挙げられます。SDSを作成するときはもちろんですが、外部からの調査依頼を受けたときなどに、必要な情報を短時間で効率的に引き出すことができる、という点はとにかく便利のひとことに尽きます。例えばEUの化学品規則・REACHを例に取ると、規制対象物質が年に何回も追加されます。それに伴い、お客様からは「今度こういう物質が規制対象になるけれど、クラレさんでは使っていますか?」といったご質問がかなり早い段階から寄せられます。
情報の一元管理がなされていなかった頃は、ともすると「ここでも使っていたのだが、つい見落としていた」ということが起こる可能性がありましたが、新たに規制対象となる物質についての情報が全社的に統合されたことで「社内のどこの部署がどんな製品に規制対象物質を使っているか」がすぐに検索できるようになったため、より確実な対応に結びついていると感じています。レギュレーション対応をより確実に行うための使い方は、情報がきちんと蓄積され、揃っているからこそ意味が出てきます。逆に言えば、情報が蓄積されていなかったり、わずかでも漏れがあったりした場合は、確認を行うこと自体に意味がなくなってしまうということです。
さらに、LOLIのようなデータベースを導入することで、関係会社や子会社などのコンプライアンスに対する意識が高まったという効果も大きかったですね。
今後の取り組みについて教えてください。
 情報の活用高度化を目指しています。
情報の活用高度化を目指しています。
取り組みとしては、化学物質管理情報の活用高度化が挙げられます。社内システムを導入し、LOLIを活用するようになってから3年。会社全体で、どんな化学物質をどう使って、どんな組成の製品をお客様へ提供しているか、という情報が蓄積されてきました。
データベースはあくまでも個別の化学物質データの集積です。それ単体でも十分に便利なものではあるのですが、複合的な管理情報があれば、それと組み合わせることでより高次元の視点から「何ができるか」「何をしなければいけないか」というさまざまな検討を行うことができるようになります。そこで現在、それらの情報を適切に整理して、より活用するための取り組みを始めているというわけです。
そのためにも、社内システムとLOLIを最大限に活用できるように今後も力を入れていきたいと考えています。情報の蓄積がデータの利用価値を高めていきますので、情報の維持・更新をしっかりと行い、より有用な情報源となるようにしていきたいですね。